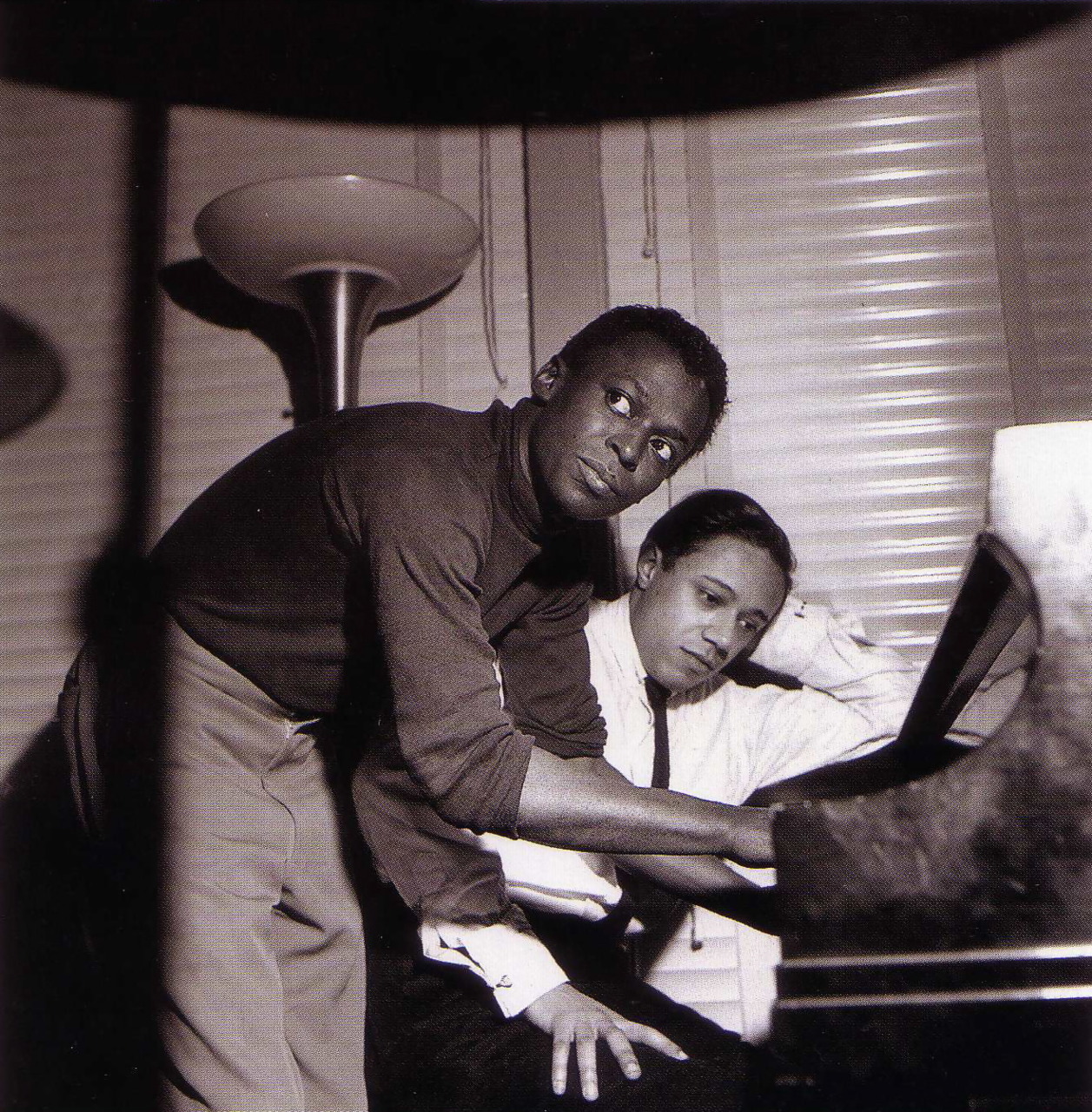- プロフィール
- Ugetsu (written by Ceder Walton)
- Firm Roots (wrritten by Ceder Walton)
- シダー・ウォルトンを知ったきっかけはベニー・グリーン(Piano)だった。
プロフィール
1937年テキサス州のダラスに生まれ。母はピアノの教師で、コンサートピアニストでもありました。よくダラスのジャズ公演に彼を連れて行ったそうです。
彼が影響を受けたピアニストは、ナット・キング・コール、バド・パウエル、セロニアス・モンク、アート・テイタムで、幼い頃から演奏を真似をしていたということです。
英語Wiki調べ
セロニアス・モンクの最初期のスタイルはアート・テイタムに近かったそうですし、バド・パウエルはモンクから理論を教わっていたそうですから、なんとなく繋がりを感じます。
また、演奏も丁寧ながらもビバップのスタイルを感じさせます。
はじめに彼の作曲した有名な曲を2つご紹介します。
Ugetsu (written by Ceder Walton)
Ceder Walton:piano
Billy Higgins:drums
Daved Williams:bass
曲名のUgetsuは、日本語の雨月(うげつ)のことです。
(日本にゆかりのある名前の曲はなんだか嬉しいですね)
Fantasy In DとUgetsuの関係性
Fantasy In Dとはなんぞや?と気になる方は多いことかと思いますので解説します。結論から言うと雨月とFantasyは同じ意味のようです。実際ジャズメッセンジャーズのライブの演奏の最初に、アート・ブレイキーがUgetsuとは日本語であり、Fantasy という意味だ。と言っています。両方の意味を知っている人からすれば、そりゃそうよと何を今更、思うかもしれませんね。ただ、私は日本人ですが、雨月=Fantasyね、はい納得、とはなりませんでした。。。調べたところ、雨月とは少し違いますが、日本には”雨夜の月”ということわざがあり、これとFantasyが近い意味でした。
雨夜の月とは、”想像するだけで見えないもの、実現しないことのたとえ”(goo国語辞書より)
という意味で
対して、Fantasyは、”現実離れした想像、幻想”(Weblioより)という意味です。
なんとなくつながりそうですね。ちなみに最後のIn DとはDのキーという意味ですね。
フレディ・ハバードと演奏するライブ映像が楽しいのでよかったらどうぞ↓
曲の由来を知って聴くとまた違った楽しみ方ができるかもしれません。
Firm Roots (wrritten by Ceder Walton)
Roy Hargrove:trumpet
Stephen Scott:piano
Ron Blake Tenor:saxphone
Rodney Whitaker:bass
Lewis Nash:drums
この曲は1974年のライブアルバムFirm Rootsで初めて公開されました。このファームルーツ、私はジャズのライブにて初めて聴いた曲で、Farm(農園)だと勘違いしていましたね。さて、Firm Rootsの意味を調べてみましょう。
Firmとは”安定した、揺るぎない”といった形容詞で
Rootsとは”人の文化的、社会的、伝統的なルーツ、土地の結びつき、や(精神的な)ふるさと”などの名詞になります。なんとなく哲学的な響きを感じますね。
Gain Firm Rootsという熟語をご存知でしょうか?、これは”強固な基盤を得る”、そういった意味になります。僕の個人的な意見としてではありますが、当時のジャズマンらにとって土地柄の繋がりが重要であったことを考えると、”同郷の仲間の深い絆”といったニュアンスなのかなとも思いました。詳しい方いれば教えていただけると嬉しいです。
(Weblio調べ)
シダー・ウォルトンを知ったきっかけはベニー・グリーン(Piano)だった。
ちなみに私がシダー・ウォルトンについて知ったのは、大学2年の終わりです。当時の私はホレス・シルヴァーが好きなのもあり、彼の曲のカバーした演奏も好んで聞いていました。その時にベニー・グリーンという比較的若い世代でビバップのスタイルを貫いているジャズマンを知り、色々聞いてみるとバド・パウエルのCelia、ホレス・シルヴァーのSplit Kick、など自分のお気に入りのニッチな曲を弾いているではありませんか!(歓喜)
彼のプロフィールなど調べたところ、バドの影響を多分に受けたと言っており、雑誌にて尊敬するピアニストはシダー・フォルトンと言っていたのを覚えています。
当時は、シダーについてはその程度しか知りませんでした。しかし去年2021年の10月ごろに入り、ジャズバーのライブ演奏で偶然聴いた曲のFirm Roots、またApple Musicにおすすめされた曲でUgetsu(Fantasy In D)との出会いでもう一度、名前を知ることになりました。実はこの2曲は去年知った曲の中でも特にかっこいいと感じたものだったんです。
両方ともたまたま、シダーの作曲で、せっかくなので記事にしてみました。少しでもお楽しみいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。